
“魂動”と名付けられたテーマの元に発信され、世界で注目を集めているマツダのカーデザイン。そのトップを務める、同社常務執行役員の前田育男氏をゲストスピーカーに迎えて行われたトークセッション。タイトルは「“Car as Art” マツダデザインのエレガンス」である。

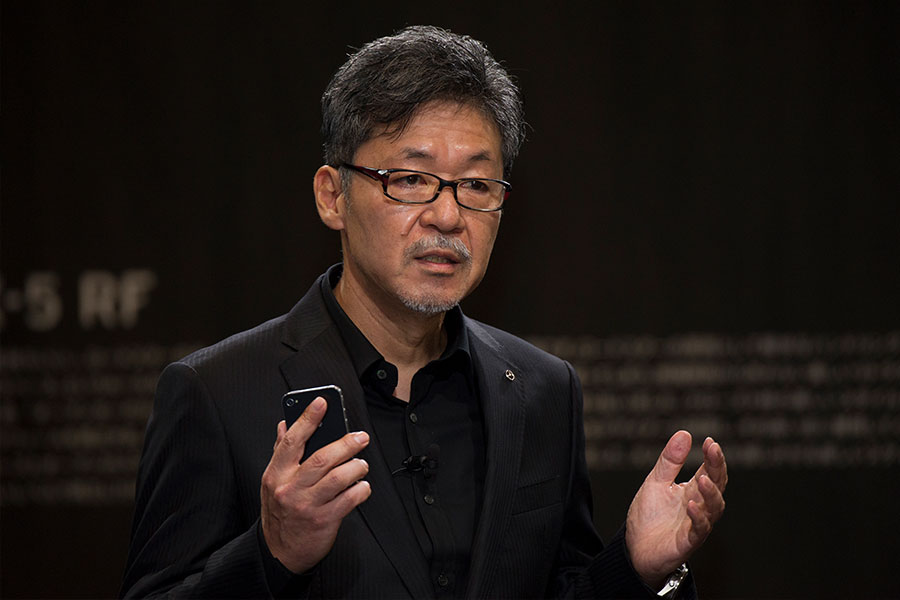



CLASSIC MEETS MODERN”というオートモビル・カウンシルのテーマに、強い共感を覚えたという前田氏。
「日本は世界に冠たる自動車生産大国。しかし、自動車文化という視点から見ると、どうだろうか? ここ数年、CLASSIC MEETS MODERNというメッセージを具体化したお手本のような海外のイベントに参加する機会が増え、欧米の大人のクルマ文化に触れるたびに、その思いを強く感じています」
その言葉のとおり、マツダは近年、海外のヒストリックイベントに積極的に参加している。2015年には、英国サセックス州グッドウッドで開催される世界最大級のヒストリック・モータースポーツイベント“グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード”の、セントラル・フィーチャーと呼ばれるテーマとなるメイクに選ばれた。会場ではルマン24時間で優勝した唯一の日本車であるマツダ787Bをはじめ、同社の輝かしいレーシングヒストリーを彩ったマシーン群が、エキゾーストサウンドを轟かせた。
「1900年代初頭のマシーンから最新のF1まで、グッドウッドの参加車両は貴重かつ高価なものばかりなんですが、参加ドライバーはみなそれらを真剣に、全開で走らせるんです。その心意気が、なんともかっこいいんですね」


イタリアはコモ湖畔で1929年から続く、世界最高峰のコンクール・デレガンスである“ヴィラデステ・コンコルソ・デレガンツァ”。2016年の同会場には、コンセプトカーのRX-Visionを展示した。
「ヴィラデステは世界中のクルマ好きのセレブリティが集まるクラシックカーイベントの頂点ですが、最新のコンセプトカーも展示され、まさしくCLASSIC MEETS MODERNな世界です。そんな最高の環境でRX-Visionがどう見えるか、勝負をかけて展示しました」



また2015年には、ベルギーのスパ・フランコルシャンで開かれた欧州最大級のヒストリックカーレース“マスターズ70’sセレブレーション”に、前田氏自らファミリアプレスト・ロータリークーペのステアリングを握って参戦した。
「自分で参加してみないと、イベントを理解することはできないと思ったからです。初めてのコースで、運が悪いことに土砂降りのなか、速いライバルに囲まれて相当ヤバい状況でしたが、必死に完走しました。わかってる、かっこいい人たちといっしょに走って、大人のクルマ文化はいいなあと心底感じられました。すばらしい経験でしたね」
こうしたイベントに参加して、デザイナーとして学ぶものがたくさんあったという。
「今のクルマは、安全、環境、効率などの課題をクリアした上で、性能的には昔より飛躍的に向上しています。しかし、こと美しさに関しては、昔にクルマに勝てていない。昔のクルマのような美しさ、味わいを、なんとか自らの手で創り出してみたいと思いました」
そしてもうひとつ、イベントに参加している人々に感銘を受けたという。
「高価なクルマを所有しているのだから、エグゼクティブには違いないんですが、みなかっこよくて、絵になるんですよ。そういうかっこいい大人を、子供たちも憧れの目で見ています。方や日本はどうかというと、若者と同様に子供もクルマ離れしている。それは我々大人たちの責任なんですね」
大人がかっこよくクルマと交わるには、かっこいいクルマ、所有するだけでかっこよく見えるようなクルマが必要。そういうクルマを創るには、過去から学び、進化させ、さらに魅力的にしていくアプローチが必要だが、はたして我々はやってきたか? と自問自答したという前田氏。マツダ自身の過去から現在に至るデザインの歴史を振り返るべく、オートモビル・カウンシルの会場に歴代モデル7台を展示した。
「現在、我々は“Car as Art”をスローガンに掲げ、アートといえるレベルの美しさの創造を目指しています。しかし、そうした発想や活動は、突然始まったわけではない。我々の先輩たちが積み上げてきたもののなかから生まれたのです」

1960年に誕生した、マツダ初の乗用車であり、日本で初めて“クーペ”を名乗ったモデルであるR360クーペをはじめ、コスモスポーツ、ルーチェ・ロータリークーペ、サバンナGT(RX-3)、ユーノス・ロードスター、アンフィニRX-7(FD3S)など歴代モデルのデザインを、前田氏は簡潔に紹介。そしてRX-7のデザインテーマとなった“ときめきのデザイン”に触れた。





前田氏によれば、デザインに特定のテーマワードを与えるのは、おそらくマツダが最初に始めたのではないかとのこと。その皮切りとなったのが、1990年代の“ときめきのデザイン”。副題を“光と影”といい、その言葉のとおり光と影が織りなすリフレクションの美しさにフォーカスした考え方が、今日の鼓動デザインの礎になったのだという。
「個人的な定義としては、クルマは単なる移動の道具ではなく、感動を呼ぶ作品、命のあるアート、心昂ぶるマシーンであるべきだと思うんです。クルマに命を吹き込むのはデザイナーの仕事で、そうした考えから“Car as Art”というスローガンが生まれました」
マツダデザインの実践にあたっては、こだわっているポイントが3つあるという。ひとつはデジタルデザイン全盛のなかで、人の手(手描き)で作りだすこと。人の手でしか生み出せないものがあり、手を動かすことによって、アーティストとしての感性が研ぎ澄まされるという。
2つめはクルマ以外のものをデザインすること。オブジェを作ってインスピレーションを得たり、自転車をデザインしたり、クルマ以外のものを手がけることでいろいろな発見があった。また他分野の人々とのコラボレーションすることによって、お互いに刺激を受け、いい化学反応が生まれたともいう。ちなみにオートモビルカウンシルの会場では、資生堂とのコラボレーションによるフレグランス“SOUL of MOTION”が披露された。これは“魂動”というテーマを、視覚のみならずほかの感覚に訴えようという考えのもと、嗅覚への訴求を具体化したものである。


そして3つめは、日本の美意識を表現したいということ。新興国からすごい勢いで新たなメーカー、モデルが押し寄せてくる現実を目の当たりにして、Made in Japanのオリジンを大事にしたいと痛感した。なかでもとくに注目したいのは、伝統的な美意識。要素を削り、簡潔に美しく、なおかつ豊かさを感じさせる、いうなれば引き算の美学。これをもう一度見つめ直し、再定義したという。
これら3つのこだわりのもとに、具体化したのがRX-Vision。2015年の東京モーターショーで初披露されたコンセプトカーである。
「要素を極力削り落とし、繊細なデザインの作り込みを行なった、最新のマツダのエレガンスがRX-Visionです。計算し尽くした、緻密なリフレクションコントロールによってのみ作られる美しさ、日本的な美の創造にチャレンジしました」
前述したように、そのRX-Visionを2016年のヴィラデステ・コンコルソ・デレガンツァに出展した。
「Car as Artと豪語する我々の作品が、世界中の目利きにどう映るか、緊張感にあふれた体験でした。屋外に展示したことで、一日の太陽の動きにしたがい、光の動きに敏感に反応するデザイン、リフレクションの変化による独特の存在感をアピールすることができました。個人的に狙っていた、大人の男の色気がある程度表現できたかと思います。会場に集まった多くのセレブリティから声をかけられましたが、そのなかに『これには日本の庭園のような緊張感を感じるね』と言ってくれた方がいたのは、感激しましたね。いよいよArtになれるかな、と感じた瞬間でした」

そのRX-Visionは、2016年1月にフランス・パリで開催された第31回国際自動車フェスティバルでモースト・ビューティフル・コンセプトカー・オブ・ザ・イヤーを受賞。続いて6月には、4大陸の自動車専門誌を代表する11名の編集者からなる審査員によるカー・デザイン・アワードのコンセプトカー部門に選ばれ、イタリアはトリノで表彰を受けた。いっぽう2015年にデビューした4代目ロードスターは、2016年のワールド・カー・オブ・ザ・イヤーとワールド・カー・デザイン・オブ・ザ・イヤーをダブル受賞し、3月のニューヨーク国際オートショー会場で授賞式が行なわれた。
「我々の作品が主だったデザイン賞を続々と受賞し、プロの目にもマツダデザインが響いたことが証明されました」


クルマは第一に移動の道具であり、メーカーにとっては製品、商品であり、販売することで利益を生まなければならない。そのクルマを取り巻く社会には、環境や安全をはじめ、課題が満載である。
「そんな時代にCar as Artなどと言っていいのか、疑問を感じないわけではなく、もしかしたら間違った目標かもしれません。しかし、もしこのスローガンが実現できれば、必ず大人がかっこよく乗れるクルマを作ることができるし、ひいては街の風景が変わっていく。私はそう信じています。そのためには、クルマに道具である以上の、もう少し深い価値を持たせたい。なにより真剣にデザインして、美しくしたいと思っています。そうすることによって、クルマが大人の文化を担う、すばらしい道具であり続けることができるのではないでしょうか」
かっこいいクルマに乗るかっこいい大人たちに触れることで、子供たちがクルマ好きになり、彼らによってクルマ文化が継承されていく。それこそが我々自動車人が果たすべき役割であると思う、と前田氏は結んだ。








